
目次
ウィスコンシン州に拠点を置くMilwaukee Tool本社に訪問
2025年7月6日から10日までの5日間、ミルウォーキーツール・ジャパン様のご招待により、アメリカ・ウィスコンシン州にあるMilwaukee Tool本社を訪問させていただきました。
Milwaukeeブランドは2021年4月に日本国内での正式展開を開始した工具ブランドです。日本市場での展開当初は自社ECサイトを中心とした限定的な販売でしたが、現在では大手販売店での取り扱いや、各種展示会・イベントへの出展も行うなど、急速に存在感を高めている注目の電動工具ブランドです。
今回の北米本社訪問ツアーは、ミルウォーキーツール・ジャパンとしても初の試みであり、日本国内の主要取扱店を対象に、Milwaukee製品の開発体制や品質管理への理解を深めてもらうことを目的としたものです。当サイトは工具販売店ではありませんが、インフルエンサー枠として特別にお招きいただきました。
この本社訪問ツアーでは、同様に工具情報の発信を行っている方も招待されており、ワサビ農家としてOPE製品を中心に情報発信を行うWASABI Channelさん、国内外の上質な工具を取扱い自ら工具情報の発信も行うファクトリーギア代表 高野倉さんと同行してミルウォーキー本社に訪問しています。
なお、Milwaukee社屋内は基本的に写真撮影が禁止されているため、本記事内で使用している写真は一部を除き撮影していません。記事的にそれだと寂しいので、現地での記憶をもとにAIで生成したイメージ画像を掲載しています。あくまで雰囲気を伝える参考としてご覧ください。
Milwaukee Tool 本社 (13135)
本社ツアーでは2つの拠点を訪問させて頂きました。そのうちの1つがブルックフィールドにあるMilwaukee Tool本社です。

本社ツアーでは、Milwaukee Toolの成り立ちや製品開発の歴史を最初に、各ブースを巡りながら、パワーツールラインの解説をはじめ、マーケティング、プロダクトマネジメント、プロダクトデザイン、バッテリー技術開発、ラピッドプロトタイピングに至るまで、多岐にわたる説明を受けました。
その内容は非常に豊富で、すべてを網羅すると記事が膨大になってしまうため、今回は実際の説明を引用しつつ、特に印象に残ったポイントを中心に紹介していきます。

パワーツールラインブース
M12やM18といったパワーツールラインについて説明を受けた後、筆者は次のような質問を投げかけました。「他社の充電式電動工具では、同じ電圧帯でもバッテリー形状を変更して製品展開を行っているケースがあります。Milwaukeeでは、そのような方針は取らないのですか?」 これに対して、以下のような回答がありました。
I can actually touch on from walking tool I actually didn’t I should have it when we launched any of our power tool lines we wanted to make sure that system compatibility stays at the core of what we’re doing whether that’s M12 M18 or MX FUEL, meaning that.Since the inception of any of those lines, you have to capability to use the same batteries you bought the original buyer tool as well as when you’re getting a new tool now. We don’t want to use it to feel that they won’t have the abilit to use the same batteries and tools.From 10 years ago.So that’s why we stick to the same battery.
当社のパワーツールラインを発売する際、システム互換性を私たちの活動の核心に据えることを重視してきました。M12、M18、またはMX FUELのいずれのラインにおいても、その原則は変わりません。つまり、これらのラインが誕生した当初から、最初に購入したツールと同じバッテリーを現在新しいツールを購入する際にも使用できる能力が備わっているということです。
私たちは、ユーザーが10年前から使用している同じバッテリーやツールを使えなくなるような状況を作りたくありません。そのため、同じバッテリーを採用し続けているのです。
この回答には、正直なところガツンと頭を打たれたような衝撃を受けました。製品開発の現場では、技術者側の道理や理屈が優先されがちであり、そのたびにユーザーの利便性やコストが犠牲になる場面も少なくありません。
筆者自身、国内の電動工具メーカーの事情や技術的な背景から、それが当たり前のことなのだと受け止めていたのですが、ここまで明確に「互換性を維持する」と言い切られると、それはある種のカルチャーショックにも近い強い印象を受けるものでした。
マーケティングブース
マーケティングでは、ミルウォーキーの製品がどのようにしてユーザーに認知されているのか、またミルウォーキーがどのようにマーケットから情報収集を行っているのかの説明を受けました。
ユーザーに対してさまざまなアプローチを行っているようでしたが、個人的に最も印象を受けたのはこの発言です。
So in the US, we do have a lot of different training Centers for all of the trends, plumbers, electricians, all of those, they’re all kind of called up here. We actually will partner with them to make sure that we can get after those users at a very early stage of our career.
米国では、さまざまなトレンドに対応した訓練センターが数多く存在し、配管工や電気技師など、それらの職種はすべてここに集約されています。私たちはこれらのセンターと提携し、キャリアの初期段階からユーザーを獲得できるよう支援しています。
例えるなら、自動二輪の教習所でホンダのCB400が使われているようなもので、その教習の経験から実際にホンダのバイクを購入するきっかけになったり、そういう訓練機関からのニーズも組み上げて製品開発に繋げている、と解釈しました。
また、北米におけるインターネット上の戦略についても下記のように発言がありました。
Another thing that we did was we partnered with influencers that were incredible third party.
私たちが行ったもう一つのことは、素晴らしい第三者であるインフルエンサーと提携したことです。
個人的な印象として、この発言は北米的な電動工具ユーザー文化を基底とするもので、日本市場で行うにはかなり難しい手法なのではないかと思っています。この辺りについては、日本とアメリカの工具情報発信の違いについて、近いうちにコラムとして執筆しようと思っています。
プロダクトデザインブース
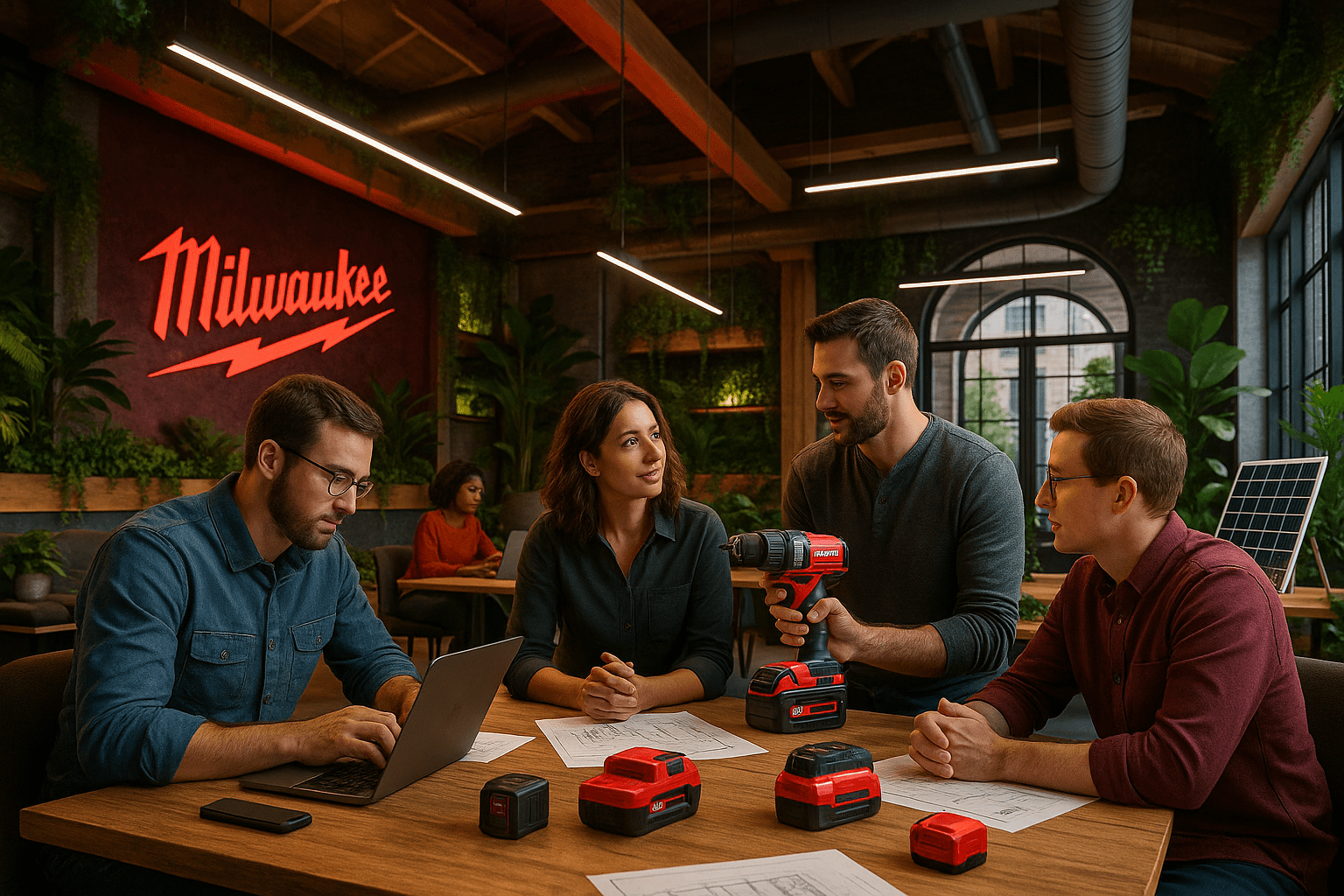
ミルウォーキー本社は開発拠点でありながら結構洒落た構造になっており、ツアーで見た部分に関してはオフィスとも工場とも言えない不思議な内装の印象を受けました。プロダクトデザインブースは特にその傾向が強く、カフェのような博物館の休憩スペースのような空港のラウンジのような不思議な空間でした。
プロダクトデザインブースでは、紙・フォームコア・テープによるモデル作りからFDM方式の3Dプリンタによる形状確認、AR技術を用いた実際の設置イメージなどを積極的に取り入れておりいました。プロダクトデザインにはBlenderなども使っているようです。
ちなみに、プロダクトデザインブースにはBambu Lab製の3Dプリンタ X1Eが置かれていました。AMSには赤色のフィラメントが装着されていたので「これはミルウォーキーのブランドカラー用に特注した赤いフィラメントですか?」と聞いたら「市販の普通の赤いやつだよ」と答えてくれました。
製品開発ブース
製品開発ブースでは、リチウムイオンバッテリーの試験設備やM18バッテリーの最新技術、モータ開発の取組などを解説してくれました。ただし、この辺りは筆者自身が内容を把握しており、Milwaukee自身が発信している技術解説周りの資料も豊富なので、技術説明そのものに関してはそこまで新しく得られるものはありませんでした。
個人的に注目したのは、製品開発に対する理念やそのプロセスについてです。
To develop our products with three major objectives in life.
製品を開発するにあたり、以下の三つの主要な目的を掲げています。
One is to target a core user.
1つはコアユーザーをターゲットにすることです。
Two is to drive innovation.
2つ目はイノベーションを推進することです。
And three is to do it faster than the competition.
3 つ目は、競合他社よりも早く実行することです。
Disruptive innovation, like I talked about before, is what truly has driven us to state that we are the world leader in cordless products.
先ほどお話ししたように、破壊的イノベーションこそが、私たちがコードレス製品の世界的リーダーであると断言できる原動力となっているのです。
We have what we call lightning speed to marketing, something that we can take within two years an idea of a product and bring it to fruition into the market within 24 months.
当社では、いわゆる「電光石火のスピード」でマーケティングを行っています。これは、2 年以内に製品のアイデアを取り上げ、24 か月以内にそれを市場に実現できるというものです。
このあたりは国内の電動工具メーカーとの比較になってしまうため、あくまで個人的な印象として述べますが、日本のメーカーは良くも悪くもスペック重視の傾向が強く、基本的にカタログ上の数値で他社製品を上回ることを目的とした開発が多いように感じています。そのため、製品開発における理念やイノベーションといった概念がやや希薄で、場当たり的な対応が目立つ印象も否めません。
そうした中で、Milwaukeeが明確なイノベーション推進を掲げ、コードレス電動工具の分野で世界的なリーダーを目指している点、そして実際にその地位に近づいている点は、評価すべきポイントだと感じました。
ラピットプロトタイピングブース
このブースでは、電動工具の試作品の製造を実際に行っているラピットプロトタイピングについて説明を受けました。内部も見学させてもらいたかったのですが、このブースは本当に機密らしく、ブース入り口の説明だけで終わってしまったのが残念なところです。
ブース内部には、ラピットプロトタイピング部門のマシニングセンタやレーザー金属焼結3Dプリンタも設置してあるようで、金属ギアボックスから樹脂成型部品まで幅広い部材の製造が可能とのことでした。
実施のブース内部の写真や詳しい解説については他のサイトで解説を行っているので、気になる方はそちらを見てみるのもおすすめです。
ちなみに、このラピットプロトタイピングの部門は週7日24時間稼働しているらしく、金曜日の午後に製造着手したRP品も月曜日の朝には設計部門に届くのだそうです。
Milwaukee Tool Red Line テストセンター (53051)
午後は本社から少し北に移動して、Milwaukee Tool Red Lineのツアーに移りました。この拠点では耐久性試験や環境試験などの各試験による製品評価を行っています。

この拠点もいくつか説明を受けましたが、膨大になってしまうので気になった点・印象に残った点を抜粋して記述します。
環境実試験(高温・低音動作試験)部屋
電動工具は熱い環境から寒い環境まで広い温度に晒される製品なので、温度に対する動作試験が必須です。
この環境実試験の部屋は面積が大きく、大型の製品であっても何台でも同時に試験できる程の規模でした。ちなみに、一部の環境試験部屋では雪を積もらせていました。
ロボットアーム(耐久試験)部屋
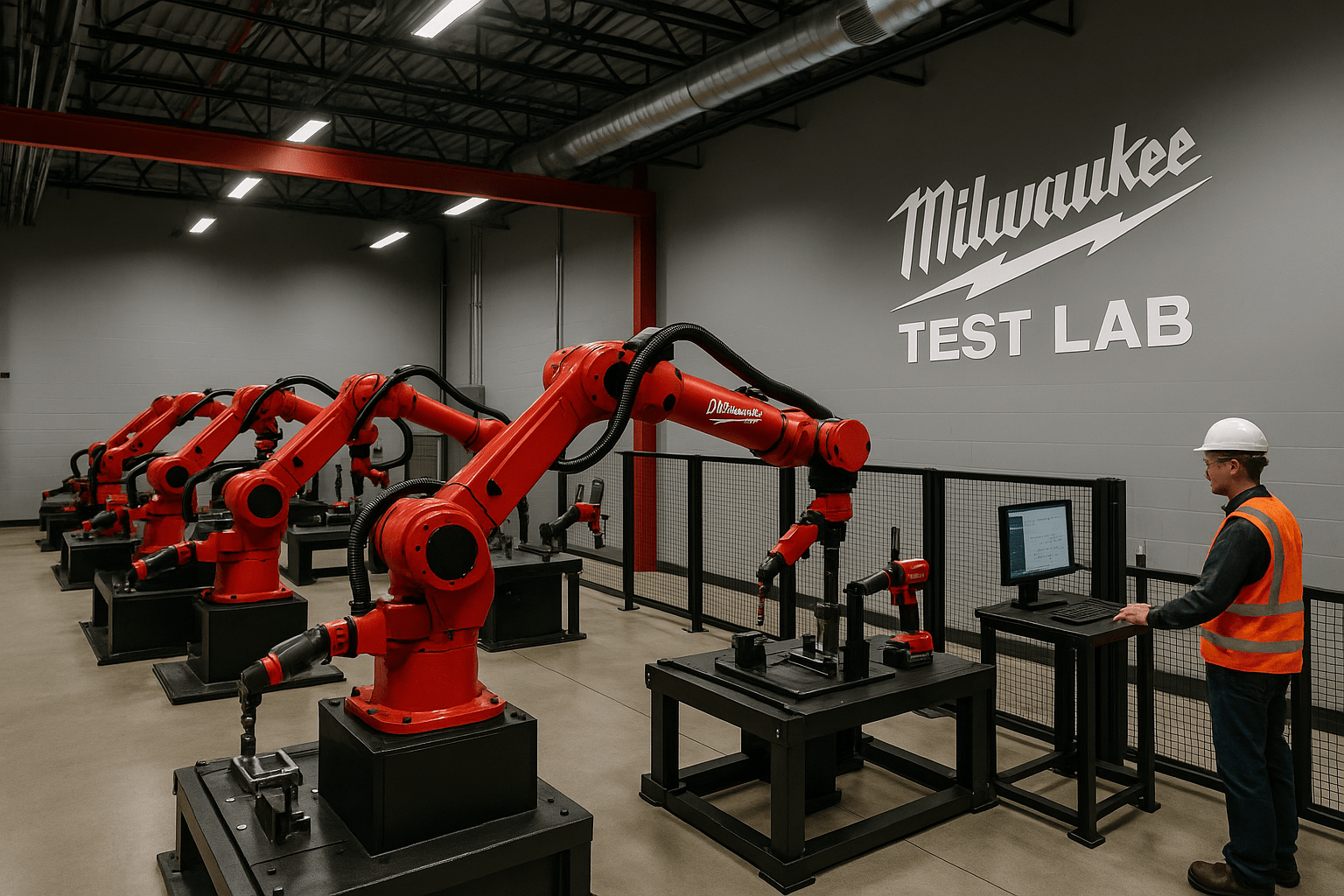
結構驚いたのが、単純耐久試験に対して使用するロボットアームの導入数です。
この耐久試験では蓋の開け閉めや摺動部品の耐久性などシンプルな動きを繰り返して耐久試験を行うのですが、ロボットアームが軽く見ただけでも10台近く導入されており、24時間体制で試験を行っていました。ちなみに、PACKOUTトローリ用の階段上り下り試験などもこのアームで実施されていました。
モーショントラフィックルーム
実際の電動工具を使用するユーザーの体の動きを捉えるモーションセンサーとカメラによって実際の筋肉の動きや重心の位置などを計測する部屋もありました。
この部屋にエンドユーザーを招いて、工具を使用している動きを見ながら、人間工学に基づいて重心や形状などを調整するケースもあるようです。
実試験&試験管理ルーム
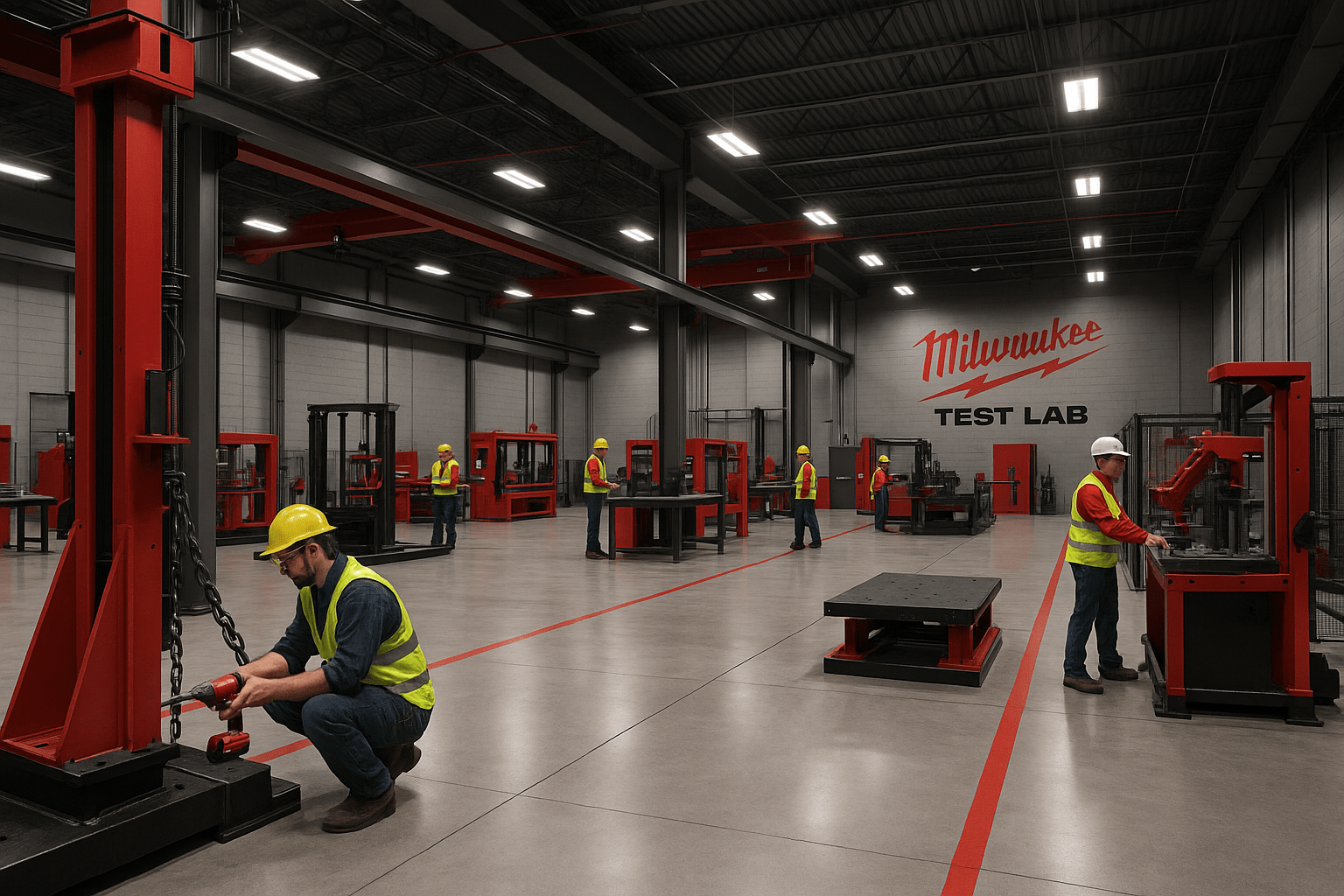
電動工具の開発には実作業を想定した耐久試験が欠かせません。この部屋では、木材の切断やコンクリートのはつりなど、実際の作業を想定した人間の手による耐久試験が行われていました。
ちなみに、この部屋の隅には試験状況を監視・管理する部屋もあり、今回訪問したRed Lineだけではなく、メキシコや中国などのほかの拠点の管理なども行っているようです。
3Dプリンタ設置部屋
本社のラピットプロトタイピングの3Dプリンタ造形に関しては、こちらの建屋に設置されているようでした。部屋に入ることはできませんでしたが、SLS(粉末焼結)方式やMJ(Material Jetting)方式の1台あたり1億円近い3Dプリンタが10台以上設置されていました。
ある意味で、ミルウォーキーツールが年間100機種以上の新製品を展開できる設備環境の一端を見れたような気がします。
研究開発と製品評価の規模でトップクラスのミルウォーキー
今回、北米ミルウォーキー本社訪問では、ミルウォーキーの研究開発における規模感やその理念などを知ることができる良い機会になりました。なぜ、ミルウォーキーが売上を伸ばしているのか、どうやって圧倒的な新製品開発ペースを維持しているのか、の理由が少しだけでも分かった気がします。
筆者は長い期間ではないものの、かつて電動工具メーカーに従事していた経歴があり、製品評価や研究開発に関して一定の見識を持っています。そうした立場から見ても、今回訪問したMilwaukee Tool本社の規模は圧倒的で、これまで見てきたどの電動工具メーカーとも比べものにならず、まさにカルチャーショックを受ける体験でした。
ちなみに、筆者は電動工具を外に持ち運んで使用する機会が少ないため、バッテリープラットフォームに対するこだわりもあまり強くありません。そういう意味で、日本の電動工具ブランドを応援したいという気持ちから国内電動ブランドを使い続けているところもあったのですが、今回のMilwaukee本社の訪問で目の当たりにした充実した設備、製品開発にかける明確な理念、そしてそれを具現化するプロダクトマネジメントの体制を見てしまうと、少なからず心が揺らぐ思いもありました。
企業としてのMilwaukee Toolに関しては、すでに経営規模の大きさや製品展開のスピード感から「ただものではない」と感じてはいたものの、実際にその現場を目にすると、想像以上のスケールに圧倒されるばかりでした。企業規模、先進的な取り組み、今後の電動工具市場の展望を踏まえても、Milwaukee Toolが今後さらに発展していくことは間違いないと確信しています。
また、ユーザー視点から見ても、Milwaukeeは常に予想を超える製品やサービスを展開しており、ユーザー自身も気づいていなかったような作業の効率化や新たな発見を提供してくれる点を評価してくれるのではないかと思います。そうした「ワクワク感」こそが、アメリカのユーザーを惹きつけてやまない理由の一つではないかと感じました。






